高橋一生×平山秀幸監督が語る『連続ドラマW 1972 渚の螢火』三度目のタッグとなるお互いの印象も明かす
2025.10.18(土)

平山秀幸が監督を務めるWOWOW連続ドラマ『連続ドラマW 1972 渚の螢火』が、10月19日より放送・配信される。原作は、『インビジブル』で第23回大藪春彦賞を受賞し、直木賞候補にもなった坂上泉のクライムサスペンス『渚の螢火』。主演は高橋一生。共演に青木崇高、小林薫、沢村一樹、城田優ら実力派俳優が顔をそろえる。
物語の舞台は1972年、本土復帰を目前に揺れる沖縄。現金輸送中の銀行車両が襲撃され、100万ドルが奪われる事件が発生。外交問題を恐れた琉球警察は極秘に特別対策室を編成し、沖縄の未来を懸けた18日間の戦いが始まる――。
史実を背景にしながら、政治と暴力、そして人間の尊厳を描いた本作。高橋と平山監督の三度目のタッグとなる本作について、二人に話を聞いた。

――高橋さんは完成した作品をご覧になったときの印象はいかがでしたか?
高橋「史実や実際に起きた出来事が下敷きにはありますが、しっかりとクライムサスペンスとして成立していました。娯楽としての強度がありつつも、重心は低く、派手な"ドンパチ"ではない。人間ドラマとしての深みがありながらアクション要素もある。エンターテインメントとしてのバランスをしっかり持った作品に仕上がっていたと思います」
――お2人が"本土復帰"という歴史的転換点を迎えた沖縄を描くこの作品に臨むにあたって、どのような覚悟や責任を意識されたのでしょうか?
平山「お話をいただいて原作を読んだときに、やはり沖縄を舞台に描くとなると、どうしても政治的なことやさまざまな思いに目がいくと思うんです。でも沖縄を舞台にする以上、それがホームドラマでもコメディでも、必ず背景には沖縄の問題が浮かび上がってくる。だからこそ、沖縄そのものをテーマにするというより、ギャング、警察、アメリカ軍といった登場人物が織りなす物語に注目しました。娯楽作品として面白そうな素材が多く含まれているので、B級アクション映画を撮るような気持ちで臨みました」
――監督自身、これまで"ドンパチもの"はあまり経験がなかったと
平山「そうなんです。だから今回はアクションをやってみようという感覚で入ったんです。政治的な題材からというより、まず娯楽性を大事にしたいと思いました」
高橋「事実をそのまま再現するならドキュメンタリーの領域になると思っています。原作をもとに娯楽として物語が作られている以上、やはり"娯楽であること"が大前提。台本を読ませていただいたときも、まずは娯楽作品としてしっかり意識しようと思いました」
――高橋さんは真栄田太一というキャラクターをどう捉えられましたか?
高橋「彼は本当にどこにも居場所がない、宙ぶらりんのような人間だと思いました。それは当時だから特別に生まれたものではなく、今もなお、社会や環境によって人が分断されてしまう現実があると思うんです。真栄田はまさにその象徴のような存在で、自分のアイデンティティすら揺らいでしまう男。しかも舞台となる1972年の沖縄自体が大きく揺れていた時代背景と重なって、その不安定さを強く意識しながら演じていました」
――セリフから滲み出る感情のゆらぎも印象的でした
高橋「セリフそのもの以上に、その"間"を大事にしました。沈黙や余白の時間こそが、人物同士の関係性や心の揺れを表すと思ったからです。与那覇といった人物と向き合うときの間合いや会話の呼吸を大切にしましたし、平山監督もそうした沈黙を丁寧にすくい取ってくださった。セリフ以外の部分で立ち上がるものを意識していたと思います」

――お2人の意識のすり合わせは、どのようにされたのでしょうか?
平山「初日のときに多少は話した気もしますが、現状や過去の政治的なことを深く話し合った記憶はないですね。むしろ"真栄田という男をどう描くか"ということを話しているうちに、自然と背景の問題に触れざるを得ないことが多かったように思います」
高橋「そうですね。政治的なことよりも、この物語をどう描くかに集中していた印象です。"エンターテインメントであるべきだ"という話は最初から共有していたと思います」
――娯楽として描く一方で、撮影が進むうちに背景の問題が見えてくる部分もあったのではないでしょうか?
平山「そうなんです。やっているうちに『そういえばこんな問題があったな』と改めて思い出すこともありました。まだ勉強不足だったと感じることもあり、逆に学びながら考えざるを得ない瞬間も多かったです」
高橋「知れば知るほど深く入り込んでしまうところはありました。物語のベースに政治的な背景が含まれているのは確かですし、それを素直に演じることが大切だと思いました。ただ、掘り下げすぎるとメッセージ性が強くなりすぎるので、僕はあくまで人物に焦点を合わせました。真栄田のように世界のどこにも居場所がない人間に寄り添っていく。その姿勢があったからブレは少なかったと思います」
――平山監督に伺います。今回で高橋さんとは3度目のタッグになりますが、改めて感じた高橋さんの魅力はどんなところでしょうか?
平山「最初にご一緒したのは『よい子と遊ぼう』('94)のときに子役で万引き強盗団を描いた作品、その次は前作の強盗団から改心して「連続ドラマW ヒトリシズカ」('12)で、警察官になる役でした。その間に高橋さんは映画でも主演を重ね、自分の世界をしっかり築いてきた。だから大きくなったねという言い方は違うけれど、映像を作る仲間として確かな存在になったと強く感じています」
高橋「監督のすごいところは、物語を作る過程で常に悩んでいることなんです。でもその悩みは迷いではなく、作品やシーンに対して誠実に向き合っている証拠。役者のお芝居をきちんと見た上で判断してくださるので、とても信頼できます。"お芝居をまず見てくれている"という安心感が常にありますね」

――平山監督は『その都度悩んでいる』とおっしゃっていましたが、具体的にはどんなところで悩まれていると感じましたか?
高橋「この作品は歴史的背景を扱っているので、リアリティをどの程度まで追求するべきか。そのバランスをまず考えられていたと思います。そして、それぞれのキャラクターがシーンごとにどう選択し、どう立ち向かうのか。その一つひとつを俳優と照らし合わせながら悩んでおられた印象です」
平山「台本はあくまで青写真でしかないと思っています。俳優の血や肉、生理のようなものが吹き込まれて初めて成立する。だから必ずしも台本通りに進む必要はありません。俳優が示したものの中から面白いと思えば取り入れるし、僕の役目はそれをどう選ぶか。悩むというのはどんな作品でも必ずありますが、特に今回は1972年の沖縄を描くにあたって、歴史の重さをどう娯楽作品として見せるか、その塩梅にはずいぶん頭を使いました」
――実際に撮影現場で台本から離れていった部分もありましたか?
平山「それは特に感じなかったですね。高橋さんだけでなく、俳優それぞれが持ち寄るものが混ざり合って、現場で一度は『これでいいのか?』と揺れることはあります。でもそれは悪いことではなく、編集の段階でどう形になるかも含めて楽しみにしていました。現場ですべてを決め切らずに、混沌の中で生まれるものを大事にしたかったんです」
――1972年当時の沖縄を描くにあたって、舞台再現にはどんな苦労があったのでしょうか?
平山「当時の風景はある程度残っているのですが、現実的には撮影できない場所も多いんです。例えば街並みを撮っても、走っている車はすべて右ハンドル。ただ、やはり沖縄ならではの空気感はどうしても出したい。その空気は東京では絶対に再現できないものなんです。それに今回は撮影時期がとても寒くて......。沖縄が舞台なので出演者は半袖を着ているのですが、実際は冷え込みが厳しく、みなさん本当に大変だったと思います。本当はもっとギラギラした暑さを映したかったのですが、そこはやむを得ませんでしたね。とはいえ、俳優のみなさんがうちわを持ち、暑そうに見せてくれたので助かりました(笑)」
高橋「現場では沖縄だから大丈夫と思って準備していたら、実際は雪が降るんじゃないかというほどの寒さで......。覚悟が足りていなかったと痛感しました。北海道のように寒い前提で準備していれば気持ちも違うのですが、今回は完全に不意を突かれた感じです。毎朝、憂鬱になるくらい冷え込みが厳しかったですね(笑)」
――今回、実際に沖縄で撮影が行われましたが、街の印象はいかがでしたか?
平山「僕は30年ほど前、助監督時代に寺山修司さんの『百年の孤独』の撮影で沖縄に行ったことがあるんです。その時はひたすらサトウキビ畑やジャングルの中を走り回っていました。今回改めて訪れて感じたのは、やはり海の美しさ、そして雲の豊かさですね。雲を撮るためだけに沖縄に来てもいいと思えるくらい、素晴らしかったです」
――沖縄の街を撮影以外で楽しむ機会はありましたか?
高橋「脚本の雰囲気や背景に引っ張られて、今回の滞在では普段見ていた沖縄とは違う"暗部"の側面を強く意識してしまいました。地元の方々に話を聞くと、アメリカにネガティブな印象を持つ人もいれば、ポジティブに捉える人もいる。その2つの間で揺れる感覚を実感しました。やはり現地に入ってこそ肌で理解できる部分がありましたね。だから街を車で通っても、どこかほの暗い印象で見ていた気がします」
平山「僕は残念ながらほとんどホテルにこもりきりで......(笑)。拠点がコザだったので、本当ならもっとエネルギッシュな街を楽しめたはずなのですが、遠出もできず、結局沖縄を満喫する余裕はありませんでした」

――共演の青木崇高さんについて、劇中では最初はライバル視し合う関係でありながら、やがてある種の共闘関係へと変化していきました
高橋「青木さんはご自身からこうやろうと芝居を組み立てるタイプではなく、その場で相手の芝居を受けながら構築していく方です。僕も自分の考えを提示しつつ、相手の出方を受けてこの関係性はどう変化するだろうと探りながら進めていました。真栄田は現地の人間から疑いを持たれる存在ですし、青木さん演じる与那覇も最初はそういう距離感を持っていた。けれど次第にそうではないかもしれないと感じ始める。そこからお互いの距離が微妙に縮まり、完全に団結するわけではないけれど、シーンごとに変化していく。その過程を芝居の中で一緒に作っていった気がします」
――改めて、共演しての印象はいかがでしたか?
高橋「実は青木さんと同じ作品でご一緒したことはありましたが、しっかりセリフを交わすのは今回が初めてでした。非常に探究心があって、現場でも『一生くんはどういう気持ちで演じてるの?』と聞いてくださる。そのやりとりを通じて、お芝居のあり方を常に研究されている方なんだなと感じました。テクニックで押すのではなく、心情の乗せ方をとても大事にされる方で、一緒に芝居をしていて面白かったですし、僕自身も学ぶことが多かったです。気づけば2〜3か月に一度はうちに食事に来ているんですよ。俳優仲間でそこまで親しくなることはあまりないのですが、青木さんとは思った以上に仲良くなりました (笑)」
取材・文=川崎龍也
放送情報【スカパー!】
『連続ドラマW 1972 渚の螢火』
放送日:10月19日(日)22:00スタート
チャンネル:WOWOW
※放送スケジュールは変更になる場合があります
出演:高橋一生
青木崇高 城田優
清島千楓 嘉島陸 佐久本宝 広田亮平 藤木志ぃさー ベンガル
沢村一樹 小林薫
原作:坂上泉『渚の螢火』(双葉文庫刊)
監督:平山秀幸
制作プロダクション:東北新社
製作著作:WOWOW
-
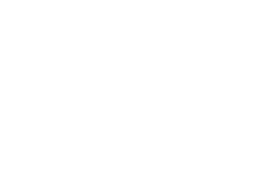
伊藤麻衣子の衝撃的な不良少女役!突出した演技力が話題となった「不良少女とよばれて」
提供元:HOMINIS3/5(木) -
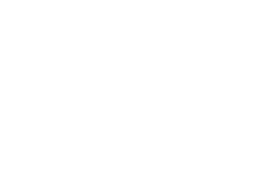
初恋のエッセンスを凝縮!映画版「冬のソナタ」でより際立つペ・ヨンジュンとチェ・ジウが織りなす切なくも甘い名シーン
提供元:HOMINIS3/5(木) -
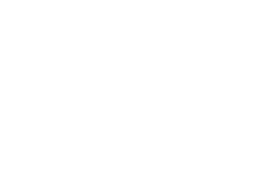
「暴君のシェフ」のイ・チェミンらに続く?「ユミの細胞たち3」への期待も高まるキム・ジェウォンが抜擢された、韓国トップ俳優への登竜門「ミュージックバンク」の歴代MC
提供元:HOMINIS3/4(水) -
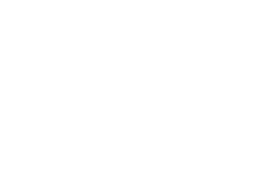
Snow Manでの姿とのギャップに見惚れる...佐久間大介が内田英治監督と共に俳優としての階段を歩む3度目のタッグ作「スペシャルズ」
提供元:HOMINIS3/3(火) -
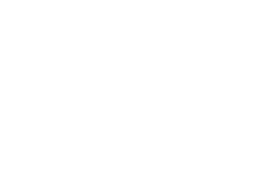
パク・ミニョンのコロコロ変わる表情に釘付け!可愛らしさ満点の姿を見ることができる「中国ドラマ「時間の都市~ロマンスはいつも予想外~」ノーカット字幕版」
提供元:HOMINIS2/28(土)


